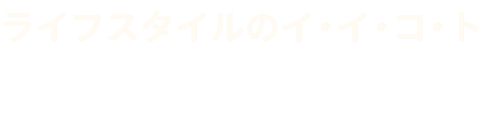酒蔵探訪 67 2010年11月
「白陽」 合名会社大谷忠吉本店
白河市本町54
Tel.0248‐23‐2030
https://www.hakuyou.co.jp/

▲大谷浩男専務
みちのくの玄関口、白河。かつて松尾芭蕉は「奥の細道」の旅に出た際に、この白河の関を越えることでいよいよ旅の覚悟を決めたという。今でこそ、高速道路や新幹線で首都圏との距離はぐんと縮まったが、東北はそれこそ「道の奥」であったのだ。「白河関跡」をはじめ、松平定信が作った日本初の公園といわれる「南湖公園」、「小峰城跡」など、白河には市内外の人々に広く親しまれている史跡、名所も多い。
そんな白河の中心部に、明治12(1879)年に創業したのが、「白陽」の蔵元、大谷忠吉本店である。ここでは創業時の面影を残す蔵で、創業から130年、変わらぬ酒造りが行われている。

▲大木英伸さん(左)と大木裕史さん

▲趣ある煙突も残る蔵
「白陽」の名は、創業間もない頃から用いられてきた。白河の「白」と、漢語で「街」を表わす「陽」を組み合わせ、また、白河を照らす「白河の太陽」を目指すという願いも込められているという。その名の通り、地元・白河に根を下ろす地酒である。「規模を大きくするなという社訓があるんです」と話すのは、5代目となる大谷浩男専務。地元に愛される酒造りにこだわる。
大谷忠吉本店の酒造りは、3つのこだわりを大切にしている。地元の所以である「米」「水」そして「人」である。米は農家と密接な関係を築き、地元の米を使う。時には自ら田に入り、品質を確かめているという。また、水は那須山系の伏流水。鉄やマンガンは含まず、カリウムやカルシウムを適度に含んだ、酒造りに適した水だ。蔵の井戸は創業以来変わらぬ場所にある。それだけ水に恵まれているという事だ。地元の米と水を原料に醸した酒だからこそ、地元の食に合う酒として地元の人に親しまれ続ける事ができるのだ。
そして、大谷専務が「最高の宝」と称するのが、酒造りを行う従業員、蔵人である。専務は先代の急逝により、若くして蔵の経営を任されたが、その後間もなく長年蔵を仕切ってきた杜氏も亡くなり、自ら酒造りも行う事になったという。「最初は大変でした。でも、蔵人や周囲の方、そしてお客様に支えられて乗り切ることができました」と、当時を振り返る。現在ももちろん、蔵人とともに酒造りに情熱を注ぐ。
そんな蔵で、若き杜氏、そして蔵頭として可能性を開いているのが、大木英伸さん、裕史さんの兄弟だ。縁あって手伝いに来た2人は、それまで日本酒はあまり飲んだこともなく、酒造りについての知識もほとんどなかったという。しかし、酒造りは、自分の仕事が酒の出来栄えという成果につながるやりがいのある仕事。どんどん面白くなり、どんどんのめりこんだという。7、8年前からは2人が酒質の設計から全行程を手掛けた「登龍」も商品化し、好評を得ている。「原点に帰る酒造りを目指しています」と、2人は言う。試行錯誤を重ねて仕込む酒は、まさにチャレンジと言えよう。大谷専務も「2人の造りがまた、蔵に、そして『白陽』にもよい影響を与えてくれています」と、その熱意を評価する。これはまた、大谷専務の挑戦でもあるのだ。
「白陽は甘口」と言われてきた。「意識してそうしてきたわけではありませんが、お客様の好みに合わせ、また、辛口が人気だった時代にもあまり味を変えずにきたからかもしれません」と、大谷専務。中辛口から甘口中心の安定した味わいが、地元の人に受け入れられているのだろう。「4年ほど連続で、鑑評会で金賞を取った事もありました。でも、うちが目指す酒は金賞ではなく、やはり地元の人に愛される酒なんです」。そう気付いて以来、鑑評会への出品はやめたという。

(左から)
・特別純米酒
・佳撰
・純米酒
・純米吟醸酒
蔵を案内していただくと、創業当時に使われていた釜や貯蔵タンク、レンガの煙突などに蔵の歴史が感じられた。聞けば昭和初期、当時の大谷家の当主、大谷忠一郎氏は詩人としても活躍していたという。萩原朔太郎に師事し、朔太郎はたびたび大谷家を訪れ、やがて忠一郎の妹・美津子と結婚したそうだ。そんな文化の香りも漂う酒蔵は、「白陽」の味とともにやはり地元に愛される存在なのだ。
※掲載されている情報は取材日時点での情報であり、掲載情報と現在の情報が異なる場合がございます。予めご了承下さい。